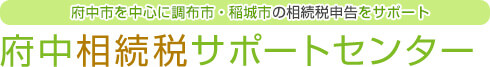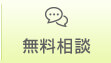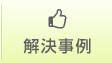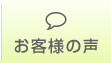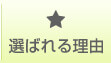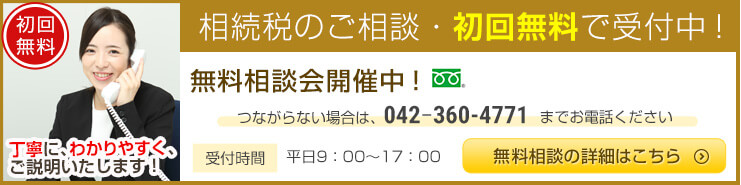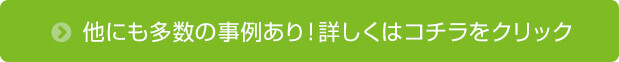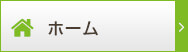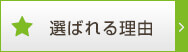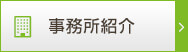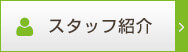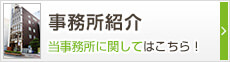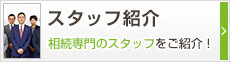贈与税基礎~の仕組み【例題をもちいて】 | 府中相続税サポートセンター
相続専門の税理士として、お子様やお孫様への贈与についてご相談を受けることは多いですが、時には別のご相談で来られた方から「数年前に子どもに贈与をして、〇〇万円の贈与税を支払いました」といった“贈与後”のエピソードを伺うこともあります。
そのようなお話を聞くたびに、「もし事前に私がご相談いただいていれば、贈与税が0円で済んだのに…。」「このように贈与すれば、もっと税金を抑えることができたのに…。」と思わずにはいられません。
税理士として、すべての方の相談に応じることができないもどかしさを感じる一方で、できるだけ多くの方が不要な税負担を避けられるよう、正しい情報をお伝えしたいと日頃から思っています。
そこで今回は、贈与税の基本から、「暦年贈与」と「相続時精算課税」のどちらを選ぶべきかのポイントについて、具体的な例題を用いながら解説していきます。すでに贈与を検討されている方はもちろん、今後の相続対策を考えるうえでもぜひ参考にしてください。

1.贈与税について
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
よって、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、直系尊属からの贈与を受ける場合等には、受贈者(もらう人)が「相続時精算課税」を選択することができます。
(1) 暦年贈与
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の価額の合計額から、暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
暦年贈与の算式: (贈与財産△基礎控除110万円)×贈与税率(一般贈与財産用と特例贈与財産用とがある)
例示:
令和6年に長男Aは、父から100万円、母から100万円の贈与を受けた。 (贈与財産200万円△基礎控除110万円)×10%=9万円 申告必要
(2) 相続時精算課税
① 基本
相続時精算課税の選択に係る特定贈与者(あげた人)ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残額に対して贈与税がかかります。
相続時精算課税の算式: (贈与財産△基礎控除110万円△特別控除2,500万円)×20%
例示:
令和6年に長男Aは、父から3,000万円の贈与を受け相続時精算課税の適用を受けるために相続時精算課税選択届出書と申告書を提出した。
父からの贈与:(贈与財産3,000万円△基礎控除110万円×△特別控除2,500万円) ×20%=78万円 届出書 + 申告必要
② 応用
相続時精算課税の選択・・・なお、同一年中に、2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合のそれぞれの特定贈与者の相続時精算課税に係る基礎控除額は、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分した金額となります。
例示:
令和6年に長男Aは、父から1,000万円、母から100万円の贈与を受け、共に相続時精算課税の適用を受けるために相続時精算課税選択届出書と申告書を提出した。
父からの贈与: (贈与財産1,000万円△基礎控除110万円×1,000万円/1,100万円△特別控除900万円)×20%=0円 申告必要→特別控除残高1,600万円
母からの贈与: (贈与財産100万円△基礎控除110万円×100万円/1,100万円△特別控除90万円)×20%=0円 申告必要→特別控除残高2,410万円
(3) 相続税の課税価格への加算
相続税の生前贈与加算(国税庁タックアンサー№4161より抜粋) 相続等によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間(注)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算します。
(注)令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となります。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって 3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年1月1日~ 令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
相法19条1項 括弧書より抜粋: (相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあっては当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する
例示:
| 何年前 | 贈与日 | 贈与額 | |
| 7年前 | 令和6年2月1日 | 110万円 | 7年前~4年前部分から100万円控除 |
| 6年前 | 令和7年2月1日 | 110万円 | |
| 5年前 | 令和8年2月1日 | 110万円 | |
| 4年前 | 令和9年2月1日 | 110万円 | |
| 3年前 | 令和10年2月1日 | 110万円 | |
| 2年前 | 令和11年2月1日 | 110万円 | |
| 1年前 | 令和12年2月1日 | 110万円 | |
| 相続発生 | 令和13年2月1日 | 7年以内生前贈与加算770万円△100万円 | |
2.暦年贈与と相続時精算課税どちらが有利か
(1) まとめ
① 過去に暦年贈与を受け、相続等により財産を取得した者は、将来的には過去7年以内のものが生前贈与加算されます。
② 相続時精算課税の場合、基礎控除を超えた部分が期間無制限で相続税の課税価格に加算されます。
(2) 有利不利の考え方のポイント
① 誰にいくらの贈与をするかで有利不利は変化する。
② そもそも相続税の基礎控除を超えるのかどうかを確認する。
③ 贈与者、受贈者の贈与契約を行う目的を明確にする。
④ 相続時精算課税は、1度適用すると暦年贈与課税には戻れない。
⑤ 贈与の場合、登録免許税と不動産取得税が相続登記より高いので注意。
大事なポイント
お子様やお孫様に多くの財産を残したい――そんな想いから贈与を検討されているかと思います。
贈与を実行される前に税の専門家にご相談いただくことで、税金を抑えられることがあります。贈与を行う際にはお気軽にご相談ください。
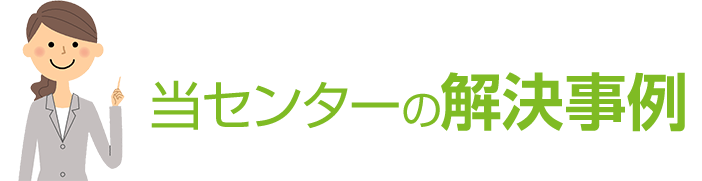
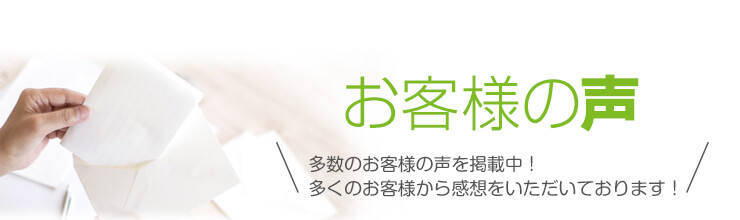
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…