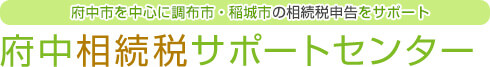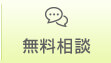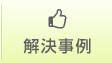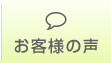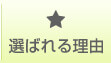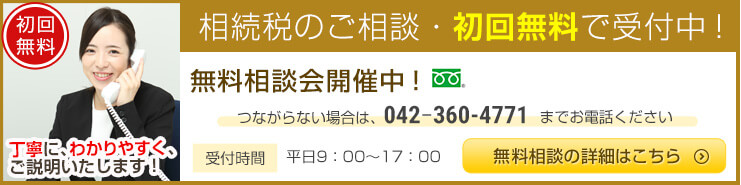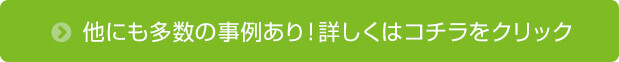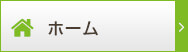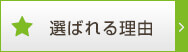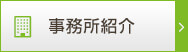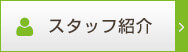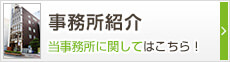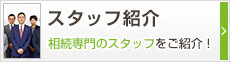相続時精算課税 | 府中相続税サポートセンター 府中相続税サポートセンター
相続時精算課税とは?
相続時精算課税制度とは、子が親から財産の贈与を受けた際に、いったんはその分の贈与税を仮払いしておき、贈与者である親が亡くなった時に、贈与を受けた財産の額を相続財産の額に加えて相続税の金額を計算し、その金額から仮払いした贈与税の金額を差し引いた残りの金額を相続税として納付するという制度です。
なお、仮払いした贈与税の金額の方が最終的な相続税の金額よりも多い場合は、相続税の申告をすることにより、払いすぎた税金を返してもらうことができます。
相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除枠がありますので、贈与を受けた金額がその累計額以下であれば、贈与税の仮払いは不要となります。ただし、この特別控除枠は暦年贈与の基礎控除額(110万円)とは異なり、相続時精算課税制度を選択してから贈与者が亡くなるまでの通算金額です。2,500万円の特別控除枠を超える贈与については、一律20%の贈与税がかかります。
加えて、2024年の改正により、相続時精算課税制度を選択している場合でも、毎年110万円までの贈与については、贈与税の申告が不要となり、その部分は相続財産にも加算されない扱いとなりました。このため、贈与を受けるたびに必ず贈与税の申告が必要だったこれまでのルールに比べ、より使いやすい制度へと見直されています。
ただし、相続時精算課税の選択初年度だけは「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要がありますので、忘れずに提出してください。
相続時精算課税制度の利用ができる人は?
相続時精算課税制度を利用することができるのは、贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母、そして受贈者が同じく1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫とされています。
贈与財産の種類、金額、贈与回数には特に制限はありません。
この制度を利用するには、受贈者が贈与税の申告期間(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)内に、所轄税務署へ「相続時精算課税選択届出書」とその対象となる贈与税の申告書、戸籍謄本などを提出する必要があります。この手続を忘れてしまうと、通常の暦年課税が適用され、高額の贈与税が課される可能性があるため、注意が必要です。
なお、2024年の改正により、相続時精算課税制度を選択していても、年間110万円以下の贈与については申告が不要となり、その部分は贈与税も課されず、相続時の財産にも加算されない扱いになりました。これにより、より柔軟に贈与を行える制度となっています。
また、この制度は、贈与者ごとに選択が可能です。たとえば、父からは相続時精算課税制度を利用して一括でまとまった財産の贈与を受けつつ、母からは暦年課税制度を使って毎年110万円の非課税枠内で贈与を受けるといった選択も可能です。
相続時精算課税制度を利用するときの注意点
相続時精算課税制度は、一度選択すると撤回することはできません。そして、選択した年以降にその贈与者から受けるすべての贈与については、自動的にこの制度が適用されます。
かつては、この制度を選択すると暦年課税の基礎控除額(110万円)を受けることができず、贈与を受けた財産の価額が110万円以下であっても、贈与税の申告が必要でした。
しかし、2024年1月の改正により、相続時精算課税制度を選択している場合でも、年間110万円までの贈与については申告不要かつ非課税となりました。これは大きな制度改善であり、従来の「少額でも申告が必要」という煩雑さが解消されています。
不動産贈与における注意点
相続時精算課税制度を利用して不動産の贈与を受けた場合、贈与者が亡くなった際には、その不動産を相続財産に組み戻して相続税の計算を行います。
ただしその際、評価額は相続時点の価額ではなく、贈与時点の価額で計算されます。そのため、たとえば贈与時に1億円だった不動産が相続時には8,000万円に下落していたとしても、相続税の計算には1億円が使われるため、結果として税額が高くなってしまう可能性があります。
さらに、生前贈与では以下のような税制上のデメリットもあります:
-
・「小規模宅地等の特例」は適用不可
・登録免許税は相続なら0.4%、贈与ではその5倍の2%
・不動産取得税は相続なら非課税、贈与では固定資産評価額の3〜4%
-
相続時精算課税制度を活かすべきケース
-
これらの制度の性質を踏まえ、相続時精算課税制度を利用するなら、次のようなケースが特におすすめです。
-
将来値上がりが見込まれる財産
→ 将来評価が高くなる前に贈与しておくことで、低い評価額で相続時の課税を抑えられる可能性があります。家賃・地代収入が見込める収益物件
→ 受贈者が収益を「先にもらう」ことができ、贈与者の財産増加を抑えられます。
一方で、そもそも相続税のかからない程度の財産しかない親から、相続時精算課税制度を使って2,500万円までの贈与を受ける場合には、贈与税も相続税もかからず、非常に効率的に財産を移転することができます。
また、2,500万円を超える贈与についても、いったん贈与税を仮払いする必要はありますが、相続時にその分が差し引かれるか、還付を受けられるため、結果として税負担がないケースも少なくありません。したがって、税金の負担を抑えつつ、財産を早期に移転できるという点で、大変有利な制度といえます。
-
詳しくは、国税庁の「⺠法の改正 成年年齢引下げ に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」をご覧ください。
相続時精算課税と暦年課税との比較
|
|
相続時精算課税制度 |
暦年課税 |
|
贈与者 |
60歳以上の父母または祖父母 |
誰でもよい |
|
受贈者 |
贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫 |
制限なし |
|
基礎控除 |
年110万円(毎年利用可) |
年110万円(毎年利用可) |
|
特別控除 |
2,500万円 |
— |
|
税率 |
非課税枠を超える部分に対して一律20% |
|
|
相続時の |
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。 |
相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。 |
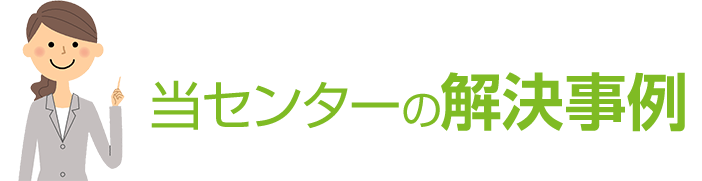
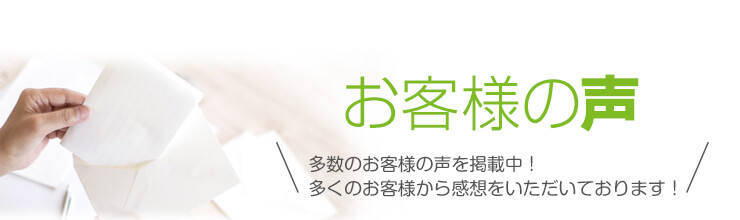
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…