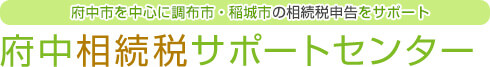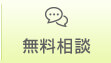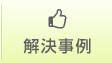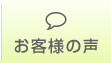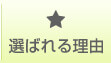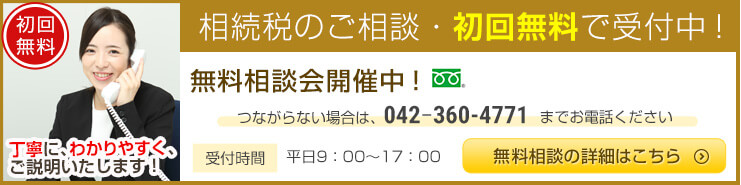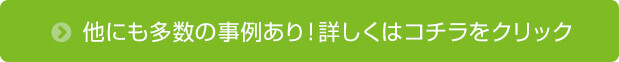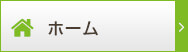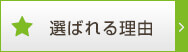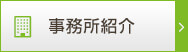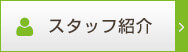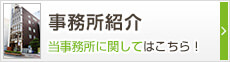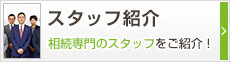離婚しました。元夫は私の相続に関係ないと思いますが、問題ないでしょうか?
フォーカス 007▶元配偶者と相続
[ 質問 ]
昨年、夫と離婚しました。法律上の婚姻関係はすでに解消されていますので、元夫(元配偶者)は私の相続には一切関係がないと思っています。この認識で問題ないでしょうか?
[ 回答 ]
離婚により法律上の婚姻関係が解消された場合、元夫(元配偶者)は、ご相談者様のご相続が開始した際の法定相続人には該当しなくなります。
つまり、ご相談者様が亡くなられた場合、元夫が自動的にあなたの財産を相続することは、原則としてありません。 この点については、ご質問者様と同様に多くの方が「離婚すれば問題がない」と考える根拠となっていると思われます。
しかし、法律上は婚姻関係が解消されていても、実は相続や相続税の世界では、元夫が関わってくるケースが「全くない」とは言い切れません。
特に、生命保険や遺言、もしくは元夫の連れ子を養子にしていたケースなどでは、元夫(元配偶者)が財産を受け取り、相続税の課税対象になる可能性があります。
そこで今回は、元夫が相続に関わってくる可能性のあるケースについて、いくつか具体的にご紹介します。
離婚後に元夫(元配偶者)が「相続人になるケース」と「相続人にならないケース」
【原則】元夫(元配偶者)は「相続人にはなりません」
離婚した元夫は、法律上の相続権を失います。
婚姻関係が終了することで、法律上の配偶者ではなくなるため、相続人の資格も自動的に消滅するからです。
つまり、仮にご相談者様が死亡しても、遺言などの特別な指定がない限り、元夫はご相談者様の財産を受け取る権利はありません。
【例外】元夫(元配偶者)が財産を受け取るケースとは?
例外ケース①:遺言書で元夫(元配偶者)に財産を渡すと明記している場合
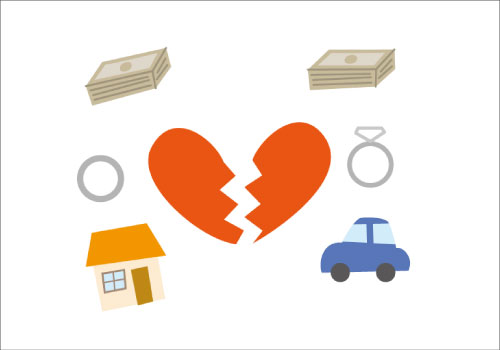
婚姻中に書いた遺言書に、「〇〇(元夫)に自宅不動産を相続させる」などの記載があれば、元夫は遺言による遺贈として財産を受け取る可能性も出てきます。
財産を受け取る人が法定相続人でない場合、「相続」ではなく「遺贈」となることから、遺言書が遺贈として有効であるかの判断は難しいところになりますので、仲が良かったころに作成した遺言書は、離婚をしたら速やかに書き換えた方が無難です。
離婚後は遺言内容の確認を忘れずに行ってください。
また、遺贈を受ける方については、相続税上、以下のような取扱いとなります。
遺贈をお考えの場合は、これらの点も踏まえてご検討ください。
【元夫(法定相続人でない方)の相続税上の取扱い】
・相続税の基礎控除額:含まれません
(法定相続人1人あたりの+600万円の加算は適用されません)
・生命保険金の非課税枠:適用対象外
・税率:相続税額が2割加算されます
例外ケース②:生命保険金の受取人が「元夫」のままになっている
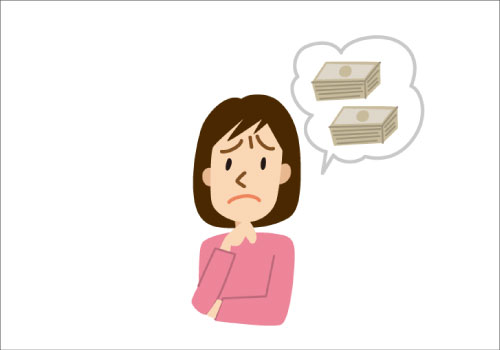
意外と多いのがこちらのケースです。
生命保険金については、「受取人に指定された人」が優先されます。
そのため、たとえ離婚していたとしても、死亡時に受取人の変更が行われていなければ、元夫が指定された通りに保険金を受け取ることになります。
生命保険契約において、契約者および被保険者がご相談者様であり、受取人が元夫となっている場合、元夫はその保険金について相続税の課税対象となる場合があります。
また、前述の通り元夫は法定相続人ではないため、
生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は適用されません。
その結果、ご相談者様の遺産総額が基礎控除額を超える場合には、元夫が保険金を受け取ることで相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要となります。
例外ケース③:元夫の連れ子と養子縁組をしていた場合

もしご相談者様が元夫の連れ子を養子にしたまま離婚し、その後も養子縁組を解消していない場合、その子どもはご相談者様の法定相続人となります。
この場合、ご相談者様が亡くなった際には、養子である連れ子が実子と同様に相続人となり、相続財産を受け取る権利があります。
相続人である連れ子が未成年の場合、親権者である元夫が「法定代理人」として相続手続きに関与することも考えられます。
これによって、間接的に元夫があなたの相続に深く関わる結果となることも考えられますので注意が必要です。
養子縁組の解消もひとつの選択肢です
元夫の連れ子と養子縁組をした場合には、「元夫と離婚しても連れ子との養子縁組は自動的には解消されません。
離婚後に「完全に縁を切りたい」と考えるのであれば、養子縁組を解消することも選択肢となります。養子縁組を解消すれば、その子どもは相続人ではなくなります。
ただし、これは法律上の手続きが必要であり、相続や親子関係に重大な影響を及ぼすため、慎重に判断する必要があります。
「離婚=完全に無関係」とは限りません
離婚によって法律的なつながりはなくなったとしても、相続税の制度や契約内容(保険・遺言など)の仕組みによっては、元夫が相続に関係してくることは十分にあり得ます。
特に相続税は、金額が大きくなると税率も上がるため、事前に対策をしておくかどうかで、他の家族にかかる負担は大きく異なってきます。
離婚後こそ「相続の棚卸し」を
離婚は人生の大きな転機です。
精神的にも、法的にも一区切りがついたように思えるかもしれませんが、実際には「相続」に関して多くのリスクや見落としが潜んでいます。
「相続なんてまだ先の話…」と思っていても、事故や病気などで突然の相続が発生することもあります。そのときに、元夫に財産が流れてしまったり、子どもの相続で誤解やトラブルが生じることも少なくありません。
そのため、離婚後にはぜひ一度、以下のような「相続の棚卸し」を行うことをおすすめします。
1. 財産の現状把握
離婚後に残った財産や負債、保険契約、名義変更が必要な資産などをリストアップし、現状を正確に把握しましょう。
2. 保険の受取人・契約内容の見直し
生命保険や医療保険の受取人が元夫のままになっていないかを必ず確認し、必要に応じて変更手続きを行いましょう。
3. 遺言書の確認・修正
離婚前に作成した遺言書がある場合は、内容が現在の希望に合っているか見直し、不要なトラブルを防ぐために修正や撤回を行いましょう。
4. 養子縁組の確認・解消検討
離婚後も養子縁組が継続している場合、相続に影響が出てきます。状況に応じて専門家と相談し、解消の必要性を検討しましょう。
5. 専門家への相談
相続税の計算や遺産分割、各種手続きには、税法などの専門的な知識が求められます。 早めに相続に詳しい税理士へ相談することで、トラブルを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。
まとめ
相続は、「感情」と「お金」が交錯する、慎重な対応が求められる分野です。
早めに専門家へ相談することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
それが、安心して将来を迎えるための大切な第一歩となるでしょう。
——————————————————-
府中相続税サポートセンターには、府中市で生まれ、調布市・稲城市にも詳しい税理士が在籍しております。
相続手続きや相続税申告のご相談も多数いただいており、さまざまなご状況でのご相続に豊富な経験がございますので安心してご相談いただけます。
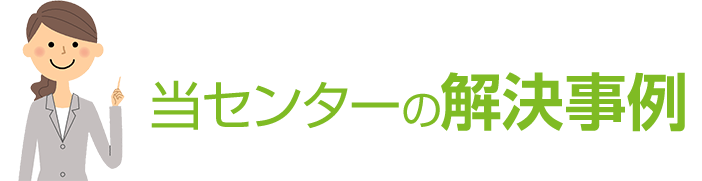
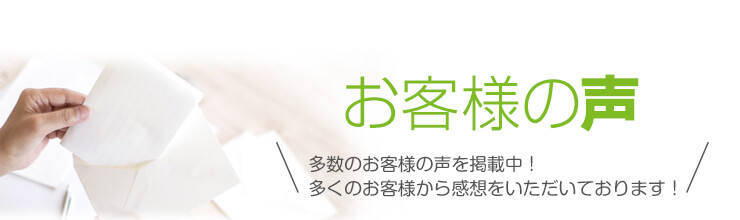
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…