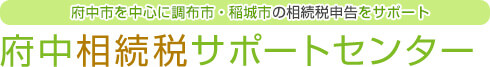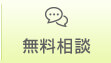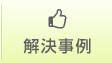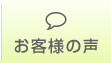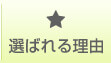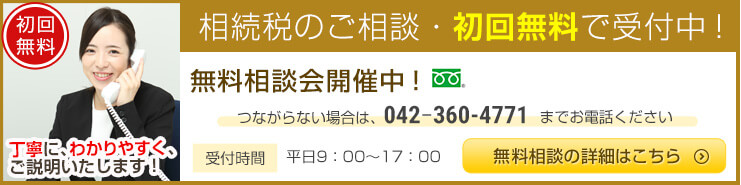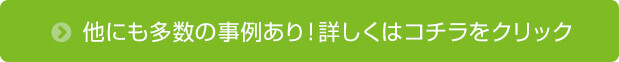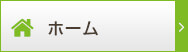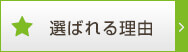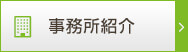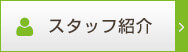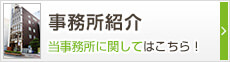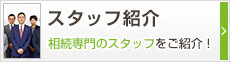再婚した夫が、夫名義の自宅とすべての預貯金を私に相続させる内容の遺言書を書いてくれる予定です。夫の連れ子からの遺留分請求が心配です。どのような内容の遺言にすればいいでしょうか。
フォーカス 004▶ 配偶者居住権
[ 質問 ]

私には再婚した夫がいます。夫には前の結婚で授かった子どもが1人いますが、私には子どももおりませんし、身近な親族もおりません。
連れ子は私たちが再婚した時点ですでに成人していたため、私とは養子縁組をしていません。
夫の連れ子と私の関係は、現在は良好です。
私には夫のほかに身近な親族もいないため、夫の死後もできる限り、連れ子との関係を良好に保っていきたいと思っています。
夫は、将来の私の生活を案じてくれていて、自分に万が一のことがあった場合、私が住み慣れた自宅にそのまま住み続けられ、安心した老後生活が送れるように、「妻に、自宅とすべての預貯金を相続させる」という内容の遺言書を書いてくれるつもりでいます。
そのように言ってくれる気持ちは本当にありがたいのですが、正直なところ少し気がかりなことがあります。
私には身寄りがいないため、夫に先立たれた場合、私の死後に財産を相続する人がいません。そのため、自分がすべてを相続しても、いずれ誰の役にも立たずに消えてしまうのではないかと考えると、少しもったいないような気がしています。
また、夫の連れ子とは現在穏やかな関係を保っていますが、夫の死後、遺言の内容によって関係が悪化し、遺留分の請求をされるのではないかという不安もあります。
 さらに夫の財産の大半は自宅不動産で占められており、自宅の相続税評価額は約8,000万円、預貯金は2,000万円ほどと聞いています。
さらに夫の財産の大半は自宅不動産で占められており、自宅の相続税評価額は約8,000万円、預貯金は2,000万円ほどと聞いています。
仮に私が遺言によって自宅と預貯金をすべて相続した場合でも、夫の連れ子には遺留分(法定相続分の2分の1)が認められているため、財産総額の4分の1にあたる分について遺留分侵害額請求を受ける可能性があると聞きました。
そうなると、夫の預貯金2,000万円のすべてを使ってもまだ不足し、私自身のわずかな財産からさらに補わなければなりません。住む家が確保できたとしても、老後の生活資金が大きく減ってしまうことはとても不安です。
できることなら、夫の思いを大切にしながら、私自身の老後の生活も安心して過ごせるようにし、同時に夫の連れ子の遺留分の問題も円満に解決したいと考えています。さらに、私の死後に残る財産についても、きちんと行き先を定めておきたいと思っています。
このような状況で、なにか良い方法があれば教えていただけないでしょうか。
[ 回答 ]
ご質問の内容を以下の様にまとめてみました。
ご状況の要点
● 夫の法定相続人は、妻と夫の実子(連れ子)1人(妻との養子縁組なし)
● 夫は遺言に「妻に自宅とすべての預貯金を相続させる」と書く予定
● 財産は1億円で、財産構成は【自宅8,000万円+預貯金2,000万円】
● 自宅は売却せずに住み続けたいというお気持ちがある
● 妻には子も、身近な親族もいないため、妻の死後の財産の行き先を考えたい
想定されるリスク
● 夫の遺言があっても、子(実子)には遺留分請求(法定相続分の1/2)の権利がある
● 自宅を相続した場合でも、遺留分請求があれば金銭で支払う必要があるため、生活費を圧迫する可能性
● 夫の死後、連れ子との関係悪化
● 妻が自宅や現預金を相続した場合、妻には相続人がいないため、妻の死後はその財産が国庫に帰属してしまう

上記の内容を踏まえ、夫の死後も配偶者である相談者様が自宅に住み続けられ、相談者様の死後には夫の実子が自宅を相続できるよう、夫の遺言によって「配偶者居住権」を設定することをおすすめしました。
さらに、妻の死後に財産の行き先を明確にしておくため、妻にも遺言書を作成することをご提案しました。
「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」とは…
自宅の「居住権」と「所有権」を分けて設定することで、亡くなった配偶者の持ち家を子どもが所有しても、配偶者(夫または妻)がそのまま住み続けられる権利のことです。
この制度は2020年4月の民法改正により創設された権利で、相続における配偶者の生活を守るために導入されました。
| 配偶者居住権について | |
| 対象者 | 被相続人の法律上の配偶者(夫または妻) |
| 設定物件 | 被相続人が所有していた建物に設定可能 |
| 設定方法 | 遺言や遺産分割協議などで設定 |
| 権利内容 | 自宅(建物)に無償で住み続けることができる |
| 権利の評価 | 相続税の評価額が「所有権」よりも低く抑えられる(=遺留分対策になる) |
| 所有権との違い | 配偶者は「住む権利」だけを持ち、「売却」はできない |
| 期間 | 原則として終身(ただし、期間を定めることも可能) |
配偶者居住権を設定することで
配偶者居住権を設定することで、自宅の評価を「負担付き所有権5,000万円」「配偶者居住権3,000万円」に分けて扱うことが可能になります。
これにより、妻は「配偶者居住権3,000万円」と「預貯金2,000万円」を相続し、合計5,000万円分を取得。一方で、連れ子は自宅の「負担付き所有権5,000万円」を相続し、法定相続分に沿った分割が実現できます。
さらに、妻の死後は配偶者居住権が消滅し、自宅の権利はすべて連れ子に移ることになります。
質問者様は、夫にご自身の悩みを解消できる内容の遺言書を作成してもらえる見通しが立ち、大変喜ばれておりました。
さらに、ご自身も死後の財産を夫の連れ子に遺贈する旨の遺言書を作成する道筋が見えたことで、将来への不安が和らぎ、心穏やかに過ごせそうだと安心されたご様子でした。
メリット・デメリット
ご相談者(配偶者居住権者)のメリット・デメリット
● 妻(夫)は生涯、家に住み続けられる
● 居住権と所有権に分けて相続税評価をするので、不動産をそのまま相続するよりも、相続税評価額が下がり遺留分請求対策になる
● 将来的に老人ホームなどへの入所を検討する際は、自宅を売却して入所資金を捻出することができないので、老人ホームなどへ入る可能性がある時は注意が必要
実子(所有権者)のメリット・デメリット
● 配偶者が亡くなれば、配偶者居住権は消滅し、完全な所有権が回復する
● 自宅を勝手に売却されたり、妻の相続人に相続される心配がない
● 土地の固定資産税は所有者に支払い義務があるため、自分が住んでいない土地の固定資産税の支払い義務が生じる
● 建物の管理や修繕費などの費用を所有権者が負担することもあり得るため、事前の取り決めが重要。
● 所有権は相続できるが、配偶者居住権が残っている間は、名義人でも自由に不動産処分できない。
⚠ 注意点
● 配偶者居住権を確実に保護するには登記が必要です。
● 配偶者居住権の相続税評価は複雑です。
配偶者居住権を相続する場合には、相続税申告に詳しい税理士にご相談ください。
府中相続税サポートセンターには、府中市で生まれ、調布市・稲城市にも詳しい税理士が在籍しております。
相続税や準確定申告のご相談や申告件数が数多く、実績も多数ございますので、どうぞ安心してご相談ください。
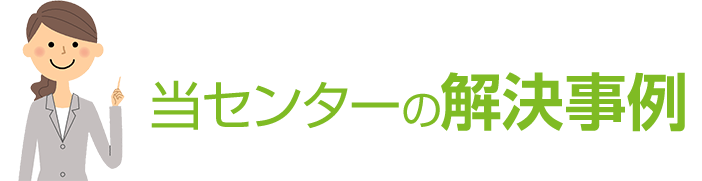
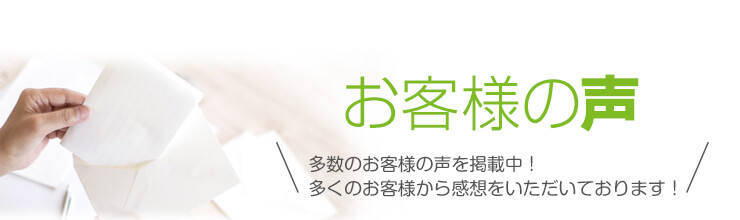
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…